|

更新の際に構造を変える事があります。 構造を変えるとアドレスが一から再配分されますので
ブックマーク等でお気に入りのページに飛んだ際に、目的と違うページが表示されることがあります。
その場合は画面一番下の [ TOP ] からトップページへ移動して、トップページから
目的のページへ移動してください。 お手数ですがよろしくお願いいたします。
トランスファー
|
|
お頼りを頂戴しました。
長文でしたので、少し削って掲載させて頂きます。
【問】 実はオートマ車に乗っているのですが,AT強化について質問があります.
JMOというアメリカの強化トルコンメーカーがありますが,強化メニューに4つのステージがあるようで
す.
ストール回転数をやや下げるステージ1から,若干上げるステージ2,さらに上げるステージ3,そして
サーキットをターゲットにしたステージ4 です.
サイトに記載されているように,トルコンにはトルクのコンバータ領域(トルクの増大作用)とロックアッ
プ領域(トルクの伝達作用)があるとのこと.
JMOだけでなくトルコン強化サイトを探してみると,ほとんどの強化トルコンは,
ストール回転数を上げる
→ コンバータ領域を高回転まで広げる
→ よりパワーがあるエンジン回転数領域でもトルクを増大させる作用を期待する
→ 加速性の向上
という記載ばかりです.
しかしながら私自身は,例えば2000rpmでストールするトルコンとは
エンジン側の回転(ポンプインペラー)とミッション側の回転(タービンライナ)数の差が2000rpmまでの
滑りを許容する(←語弊があるかも) トルコンというふうに理解しています.
それ以上の回転数差はそのエンジンの出力では滑りを許容できないということだと思うのです.
またその2000rpmの回転数差のときがそのトルコンのトルク増大作用の最大値だと思うのです.
逆に回転数差が減ってくるにつれロックアップ領域に近づくというふうに理解しています.
ところがストール回転数が3000rpmのハイストールトルコンがあったとすると,エンジン出力が同じ場
合,3000rpmの回転数差まで滑りを許容するということになります.
そして3000rpmの回転数差のときがトルク増大作用が最大と考えられますよね.
ここで疑問が湧きます.
ハイストールトルコンの方がノーマルトルコンよりも滑りを許容する.すなわち滑りやすい? 滑りやす
いトルコンで加速性が良くなるのか?
あるいは2000rpmでストールするトルコンのトルク増大作用よりも,3000rpmでストールするトルコンの
トルク増大作用の方がずっと大きいと考えるのが正解なのでしょうか?
どうにも矛盾に感じるのです.
明解なご回答がいただけると幸いです.
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽
【答】トルコンAT車でクルマが止まっている時に、ブレーキペダルを強く踏みながらアクセルペダルを
踏み込むと、タイヤが回ってっていないのにエンジン回転数が高くなります。
この時、ポンプインペラーからタービンライナーへ流れたATフリュードはタービンライナーを回せずに
タービンライナーから出て行くことになってしまいます。
当然のことながら、そのフリュードの流れる勢いは強く、ステーターを介してポンプインペラーへ戻り、
更にポンプインペラーで加速されてまたタービンライナーへ流れます。
この繰り返しで止まっている駆動系に掛かる力がエンジンの出力トルクよりも大きくなります。
先に説明した通り、「止まっている駆動系に掛かっている力」は、
ポンプインペラー → タービンインペラー
↑ │
└── ステーター ←─┘
の繰り返しで増大しているのですから、2000rpmでストールするトルコンよりも3000rpmでストールする
トルコンの方が「止まっている駆動系に掛かっている力」が大きくなります。
そして、エンジン回転数を高めたまま、ブレーキをリリースするとエンジン出力よりも大きな力(=トル
ク)で急発進するのですが、当然のことながら、「止まっている時に駆動系に掛かっていた力」の大きい
方が猛烈急ダッシュすることが可能になります。
だから2000rpmでストールするトルコンよりも3000rpmでストールするトルコンの方が急発進できるの
です。
★追伸:上述の説明に於ける「止まっている駆動系に掛かっている力」と「エンジンの出力トルク」の比を
“ストールトルク比”と呼びます。
つまり、トルコンAT車でクルマが止まっている時に、ブレーキペダルを強く踏みながらアクセルペダルを
踏み込んだ際に、「止まっている駆動系に掛かっている力」は
エンジントルク×ストールトルク比
によって求められます。
- - 2010.01.27 → 2010.01.31改 → 2010.02.03図を訂正 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ちょっち補足。
ポンプインペラー,タービンインペラー,ステーターの関係を簡単に説明しておきましょう。
トルクコンバーター内に於けるATフリュード(ATフィールドではないぞよ)の流れと作用は、ちょうど玩
具【トミカびゅんびゅんサーキット】に置き換えることができます。
サイト内画像のローラーゲートがポンプインペラーで、
ローラーゲート(※)に拠ってカタパルト的に加速されて走っているミニカーがATフリュードです。
※注意:トルクコンバーターをトミカびゅんびゅんサーキットに見立てた場合、
ローラーゲートは俯瞰図下側の1個だけになります。
いつものように、エクセルのオートシェイプで絵を描いてみました。
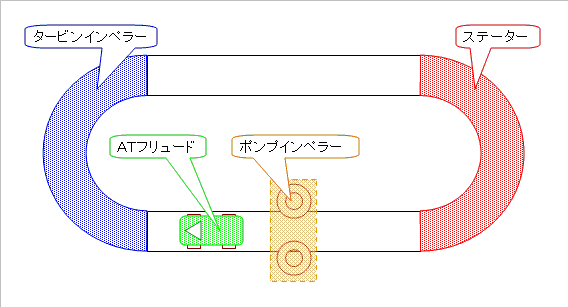
モーターで回る円筒形のスポンジでミニカーを加速するローラーゲートが「ポンプインペラー」,
絵の左側にあるカーブが「タービンインペラー」,
絵の右側にあるカーブが「ステーター」,
そしてミニカーが「ATフリュード」に相当します。
ミニカー(ATフリュード)は、ローラーゲート(ポンプインペラー)により加速します。
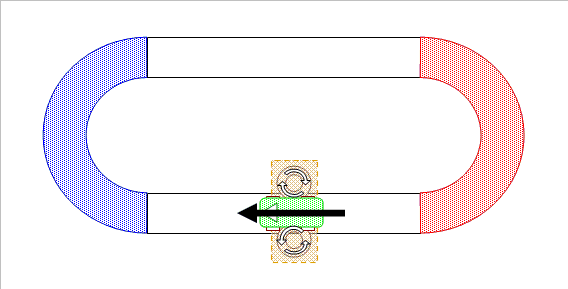
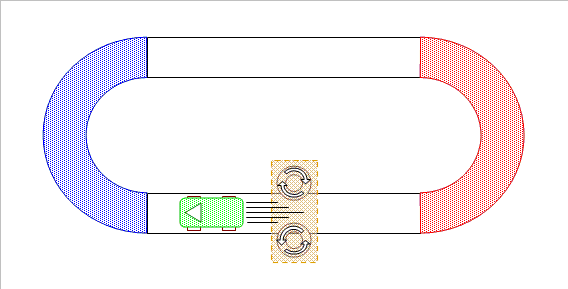
ミニカーがカーブを曲がる時、遠心力で外側の壁を押します。
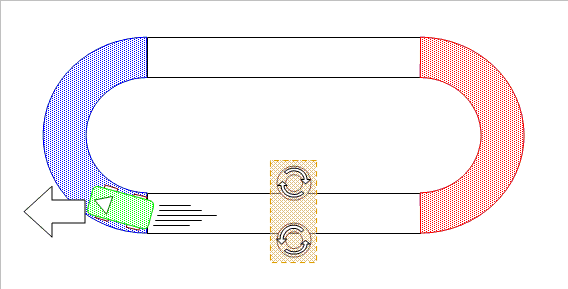
クルマが走っていて、ポンプインペラーとタービンインペラーの回転差が少ない時、ATフリュードはそ
の運動エネルギーでタービンインペラーを推します。
びゅんびゅんサーキットで言えば、左のカーブ(タービンインペラー)がミニカー(ATフリュード)に推さ
れて、左方向へ動いてしまうような状態です。
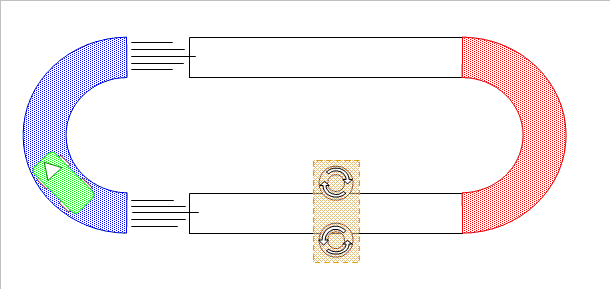
ブレーキが強く踏まれてクルマが静止している状態は、左のカーブが直線部分に繋 がれて(結合さ
れて)いる状態です。
この時ミニカーは、左のカーブ(タービンインペラー)を曲がり切り → 絵の上方直線部分を右方向に
疾走し → 右のカーブ(ステーター)を通過します。
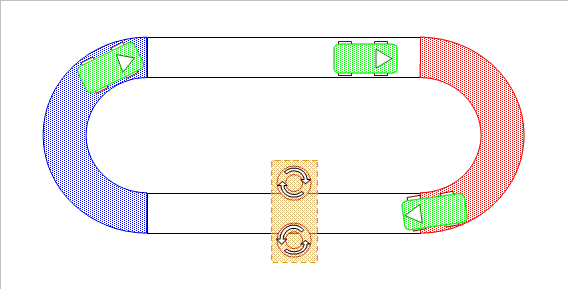
トミカの玩具は、幾らローラーゲートの回転力を上げてもミニカーが一周して来て速度が余りある、と
い う状態になりませんが(その前にミニカーがコースを飛び出してしまう)、ATフリュードの場合は、ポ
ンプイ ンペラーで加速されたATフリュードがタービンインペラー → ステーター → 再びポンプインペラ
ーに戻っ てきた時に十分な流速を残しています。
ですから、タービンインペラーを止めたままポンプインペラーでガンガン加速してやると、ATフリュード
の 運動エネルギーがドンドン大きくなり、非常に強い力でタービンインペラーを押します。
トミカの玩具でいえば、目にも止まらぬ速さでミニカーがコース内を疾走して、カーブの壁がミニカーで
ゴリゴリと削られているような、そういう状態になるワケです。
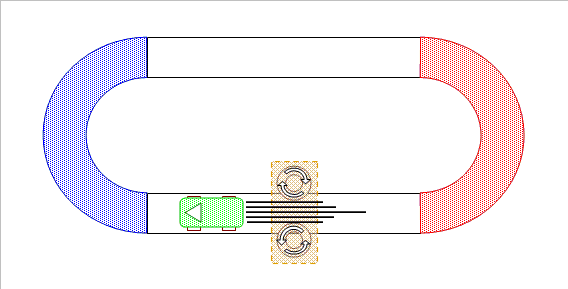
この状態でタービンインペラーの拘束を解く(=ブレーキペダルをリリースする)と、タービンインペラー
は エンジンの出力トルクよりも強い力で回されるので、クルマが急発進するのです。
(トミカの玩具でいえば、目にも止まらぬ速さでミニカーがコース内を疾走している時に、左カーブの取
り付け部分を切り離したら、凄いスピードのミニカーに押されて左のカーブが勢い良く飛び出してしまう
ような状態です)
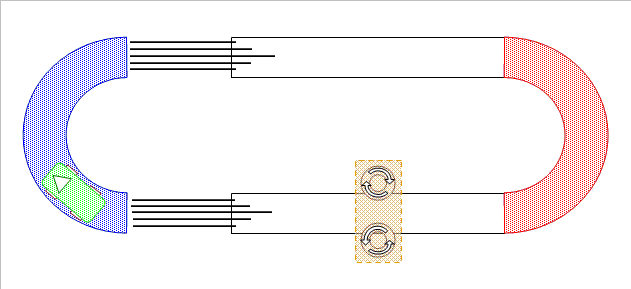
という理屈で、ポンプインペラーとタービンインペラーの回転差によってトルクコンバータはトルク増幅
作 用を得ているのです。
これ以上の説明は書籍をご覧ください。
2012.07.31
図解してくれる本が発売されました♪
↑コレの102ページに一目で分かる図解が載っています。 是非御一読下さい。
|
|
|

|