|

更新の際に構造を変える事があります。 構造を変えるとアドレスが一から再配分されますので
ブックマーク等でお気に入りのページに飛んだ際に、目的と違うページが表示されることがあります。
その場合は画面一番下の [ TOP ] からトップページへ移動して、トップページから
目的のページへ移動してください。 お手数ですがよろしくお願いいたします。
サスペンション
| スタビライザーの強化a (2007.05.03 計算式訂正)
|
|
【問】 【バネレートの高いスプリングとそれに応じたダンパーのみ装着車両(以下【サスキット】と略す)】と
【強化スタビのみ装着車両(以下、【強化スタビ】と略す)】を比べた時に、もし同じ姿勢で旋回していると 仮
定するなら、両者の何が違うのでしょうか?
★▲▼■◆●☆△▽□◇○★▲▼■◆●☆△▽□◇○★▲▼■◆●☆△▽□◇○
話を理解し易くするため、仮の数値を想定し、まずは荷重移動について検証してみましょう。
(なお、計算がややこしくなるので、ロールに因って生じる質量の偏りは考慮しません)
車両重量1200kg、重心点高さ0.5メートル、トレッド1.5メートルのクルマが1Gという限界に近い旋回速
度で加減速なく定常円旋回状態にある時、
[ 遠心力 ] = 1200(kg) × 1(G) (= [ 四輪のコーナーリングフォースの総和 ] )
したがって、
[ 車両全体に対するロールモーメント ] = 1200(kg) × 0.5(m) = 600(kg・m)
この時、
[ 荷重移動 ] = 600(kg・m) ÷ 1.5(m) = 400(kg)
このクルマの前後重量配分が50:50だと仮定すると、前二輪もしくは後二輪における荷重移動は
200kgになります。
強化スプリングのバネレートが12kg/mm程度なら、ダンパーのガス圧やブッシュの捻りに対する反発
力、レバー比などを考慮してアウト側のサスペンションは平衡状態から15mmくらい縮むでしょう(← ちょ
っちイイ加減な憶測)。 もちろん、イン側のサスペンションは同じだけ伸びます。
ノーマルのバネレートが6kg/mm程度なら、サスペンションストロークの変化は、伸び縮み共25mmくら
い だろうと想定されますが、これをスタビライザーで15mmに抑えるものとします。
スタビライザーの仕事はロール抑制です。
ロール抑制をスタビライザーの強化で行うことのメリットとして
(1)サスペンションスプリングの強化よりも乗り心地が良い(悪くならないワケではない)。
(2)普通のクルマはホイールベース幅とトレッド幅が大きく違うため、同じ水平Gでもダイブ/スカ
ット量とロール量が大きく異なる。
スタビライザーの調整(強化というよりも適正化)は、これを補正することができる。
(3)(2)の補正によって同じ水平Gに対するダイブ/スカット量とロール量を近づければ、ドライ
バーが体に感じたGに応じてクルマが姿勢変化するため、クルマの挙動を掴み易くなる。
を挙げることが出来るでしょう。
以上のように考えると、【強化サス仕様車】と【強化スタビライザー仕様車】が同じ姿勢で旋回し得ま
す。 では、同じ姿勢で旋回する2車の何処が違うのでしょうか?
次に【強化スタビ】のデメリットについて。
実際にサスペンションを弄ったことのある皆さんは知っているはずです。 「【強化スプリング(+強
化ダンパー=サスキット)】と【強化スタビ】の挙動特性は違う」ということを。
何故でしょう?
サスペンションにおけるダンパーの役割・機能を考慮すれば、【強化スタビ】は【サスキット】より も不
利になります。
スタビライザーは捻りバネとして左右のサスペンションアームを繋いでいます。 一方のサスペンシ
ョ ンが路面からの入力に因って縮むと、捻りバネがもう片方のサスペンションを縮める仕組みです。
捻り"バネ"ですから、捻られたバネが入力から解き放たれると固有振動数でビヨ〜ンビヨ〜ンと跳
ね ます。 このように、入力を受けたバネがビヨ〜ンビヨ〜ンと跳ねるのは、サスペンションスプリン
グも 同じです。 しかし、サスペンションスプリングは、各々がダンパーという減衰装置を有しており、
振動 する運動エネルギーが速やかに消費されます。 ところが、"スタビライザーの振動を減衰する
ための 装置"はありません。 スタビライザーは、サスペンションスプリングのための減衰装置"サス
ペンショ ンダンパー"を使って振動を減衰するのです。
ということは、スタビライザーを装着した車両のサスペンションダンパーは、「サスペンションスプリン
グ の振動」と「スタビライザーの振動」の両方を減衰しなくてはなりません。 このため、スタビライザ
ーを 装着した車両は、サスペンションのセッティングがし難くなってしまうのです。
もう少し具体的に話しましょう。
サスペンションスプリングのバネレートと軸重から要求される減衰力が大まかに決まります。 これ
は、バネの反発力と質量から要求されるエネルギー損失度が決まるからです。 しかし、スタビライ
ザ ーの反発力は、もう一方のサスペンションとの位置関係(ストローク差)によって異なるため、要求さ
れ る単位ストロークあたりの減衰量が千差万別に変化します。 スタビライザーの捻れ量が小さけ
れ ば、要求されるエネルギー損失度はサスペンションスプリング単体の時と大差ありません。 しか
し、 スタビライザーの捻れ量が大きければ、要求されるエネルギー損失度はサスペンションスプリング
単体 の時よりも格段に大きくなければならないのです。
つまり、サスペンションスプリングのバネレートに比べてスタビライザーを強くしたクルマは、キチンと
セッティングを出すことが不可能となり、『速い足まわり』に仕上がらないのです。
さて、話はマダ続きます。
おそらく、コレがスタビライザー強化によるグリップ力低下の最大要素だと思われるのですが、スタビ
は、片方の車輪の上下運動を、もう片方へ伝えてしまいます。
公共投資を浪費し続けることを目的として、不要な掘り返しを繰り返す一般公道はもちろん、サーキ
ッ トにおいてさえも路面は大小さまざまな凹凸によって構成され、そこかしこにウネリや歪みが存在し
てい ます。
これは、車体側面に設置されたビデオカメラの映像として、月刊あるいは季刊のビデオマガジンなど
でご覧になった貴兄も多いことでしょう。
ドライバーとして極めて平滑な路面だと認識されるサーキットでさえ、市販車のサスペンションは激し
く 上下運動を繰り返しているのです。
実は、強化スタビは、そのような路面変化に全く向いていません。
その理由は、片側の車輪が上下運動することによって、もう一方の車輪も上下運動させられてしまう
ことにあります。
スタビライザーは捻りバネとして左右のサスペンションアームを繋いでいます。 一方のサスペンシ
ョ ンが路面からの入力に因って縮むと、捻りバネがもう片方のサスペンションを縮めます。 これによ
っ て、入力のあった側の"見かけ上のバネレート"が高くなり、ロール角が抑制されるわけです。
しかし、この構造は、必ずしも旋回中における左右輪の荷重差に対してのみ機能するのではありま
せん。
左右輪間に不均一な入力があれば機能してしまうのです。
それはたとえば、旋回中に内輪が縁石を踏む・・・サーキット走行では良くあるシチュエーションです
が・・・この場合も、縁石の凸がイン側のサスペンションを縮めた瞬間に、スタビライザーがアウト側の
サスペンションも縮めてしまいます。 このため、瞬間的にアウト側タイヤの接地圧が下がって、両輪
の求心力和が小さくなってしまう現象が起こるのです。 フロントタイヤの内輪が縁石を踏めば瞬間
的 なアンダーステアを呈し、リアタイヤの内輪が縁石を踏めば瞬間的なオーバーステアを呈することに
な ります。
そして、このような現象は、必ずしも「旋回中に内輪が縁石を踏む」というシチュエーションに限られる
わけではありません。 凹凸やうねりのある路面において、左右輪が同時に凹みに嵌ったり、凸に乗
り上げたり、うねりが同調したりしない限り、極当たり前に生じる現象なのです。
つまり、凹凸もウネリも全く無い理論上の路面であれば話は別なのですが、たとえ(一見平滑に見え
るサ ーキットであっても)実際に走行する路面は(程度の差こそあれ)大小様々な凹凸やうねりに満た
されていま す。 同じようにロール剛性を向上させるサスペンション強化(バネレートUP&それに見合
った減衰力)に比 べて、実走行の限界は下がってしまいます。
要するに、理論上の仮想路面ではない現実の路面に【強化スタビ】は向いてい ないのです。
もっとも、だからと言って元々ノーマル状態で装着されているスタビを外しても良いというワケではあり
ません。
大昔のCR-Xみたいな特殊なクルマは別にして、普通のクルマはタイヤのホイールベース幅よりもトレ
ッド幅の方が遥かに短いため、サスペンションスプリングに因るダイブ/スカット抑制よりもロール抑制
の方が効き難くなります。
スタビは、そのバランスを取る役割も担っていますので、【強化スタビ】が現実の路面に適していない
からと言って【ノーマルのスタビ】まで否定すべきではありません。
また、「ダイブ/スカット抑制とロール抑制のバランスを取る」という意味で言えば、サスペンションスプ
リングを強化することによってダイブ/スカット抑制とロール抑制のバランスが崩れた場合、適切なバネ
レートのスタビに換えてバランスを適正化するのは良いことだと思います。
・・・以上が、現時点で圭坊の捉えている「【サスキット】と【強化スタビ】の違い」ですが・・・
さらに、特殊な使い方(前後いずれか片方だけを強化あるいは弱化
する)をした場合のスタビライザーがどういう効果をもたらすかについ
て、追加の説明を致します。
あまり一般的なセッティングではないので割愛していましたが、稀にこういうデチューンをする人も居
るようなので、書かせて頂きます。
話を簡単にするため、ロワアームジオメトリのロール抑制効果やブッシュ&スタビの介在などは全て
無視します。
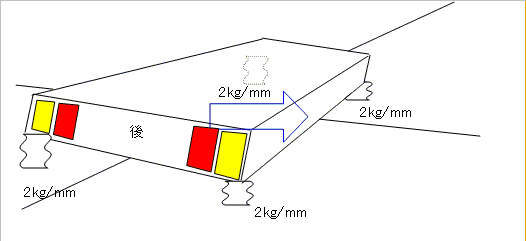
余り上手な図にならなくてゴメンナサイ(メチャ面倒臭いんですYO)。
コレ↑でもクルマのモデル図のつもりです。
(もちろん、表記のバネレートはホイールレート)
青色の矢印が遠心力で、遠心力を受けて右側のスプリングが縮んでいます。
クルマの重さが1200kgなら、この時のクルマ全体の荷重移動量は、
重心高:50cm(0.5M)、
トレッド幅(タイヤ接地面両端部幅):1.5M
のクルマが遠心力:0.5Gで旋回するとき、
[ 遠心力 ] = 1200(kg) × 0.5(G) = 600(kg)
[ 荷重移動量 ] = 600(kg) × 0.5(M) ÷ 1.5(M) = 200(kg)
です。 繰り返し述べてきた通り、バネの伸縮に伴って重心が移動する点(=質量の偏り)を無視す
れば、バネレー トは荷重移動量に影響しません。
重心位置が俯瞰してセンターに在るなら、前輪が負担する荷重の移動量は後輪が負担する荷重の
移動量と同じです。
車両全体の左右方向への荷重移動量が200kgということは、アウト側の荷重が100kg増えて、イン側
の荷重が100kg減ったということです。
ちなみに、この時のロール量は右側前後のバネが荷重移動100kgを受けて縮み、左側前後のバネが
荷重移動▲100kgを受けて伸びます。
車両片側のバネレートは 2(kg/mm:前) + 2(kg/mm:後) = 4(kg/mm) だとしたら、
右側が 100(kg) ÷ 4(kg/mm) = 25(mm) 縮んで、
左側が 100(kg) ÷ 4(kg/mm) = 25(mm) 伸びます。
さて、ではこの車両のフロントサスペンション「だけ」に【強化スタビ】を装着したらどうなるでしょうか?
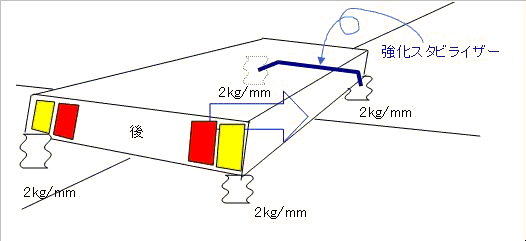
クルマ全体の荷重移動量は変わりません。 この場合も、
車重:1200kg
重心高:50cm(0.5M)、
トレッド幅(タイヤ接地面両端部幅):1.5M
のクルマがG:0.5で旋回するとき、
[ 遠心力 ] = 1200(kg) × 0.5(G) = 600(kg)
[ 荷重移動量 ] = 600(kg) × 0.5(M) ÷ 1.5(M) = 200(kg)
です。
ところが、フロントタイヤの強化スタビライザーがロールを抑制するために、ロール量が減ります。
もし、フロントに装着された強化スタビライザーの効果に因ってロール量が半減され、その結果として
右側が 12.5(mm) 縮んで、左側が 12.5(mm) 伸びたとしたら、どうでしょう?
後輪にしてみれば、フロントサスペンションのスタビライザーさえ強化されていなければ 25mm縮むこ
とが出来たハズなのに、「前輪の強化スタビライザーが支えることに因って(スタビライザーがノーマル
の時に比べて)ロールが抑制されている」と見ることが出来ます。
さて、理解して頂くために少しだけ違う話をします。
たとえば、バネ秤に100gの物を載せて、皿の高さが5cm沈んだとします。
突っかえ棒か何かを当てて皿の降下量を半分に抑えたら、秤の針が示す数字は、50gです。
もうだいたいオチが読めてしまったと思いますが、一応未だネタバレしていないという前提でハナシを
進めます(笑)。
スタビライザーがノーマルの時、右側が 25(mm) 縮んで、左側が 25(mm) 伸びていました。
強化スタビのおかげで、50kg/mmを受けて本来なら25mm伸び縮みしているハズのリアサスペンショ
ンが、フロントの強化スタビライザーに邪魔されて12.5mmしか伸び縮み出来なくなっているワケです。
先ほどのバネ秤の例は、荷重を受けて縮む量が減らされたために、秤のメカへ伝わるべき荷重が
減 らされてしまい、結果として秤の針が指す数字が小さくなっていました。
それはクルマのサスペンションでも同じです。
荷重を受けて縮む量が外部(この場合は前輪のバネ)の影響を受けて減らされると、タイヤに伝わる
荷重が減るのです。
もちろん、この物理は伸び側にも作用しますので、荷重を受けて伸びる量が外部(この場合は前輪の
バネ)の影響を受けて減らされると、タイヤに伝わる荷重が増えます。
計算上は、本来なら25mm縮んでいるハズのリアサスペンションが、フロントの強化スタビライザーに
邪魔されて12.5mmしか縮まないのですから、リアタイヤに伝わる荷重移動量は50kgではなく25kg。
片側前後輪で100kgも荷重移動しているのに、後輪が25kgしか荷重移動をタイヤに伝えていないので
すから、前輪のタイヤに伝わる荷重移動は
100(kg) − 25(kg) = 75(kg)
となります。
伸び側(イン側:上図では左側)でも計算式は同じで、リアタイヤに伝わる荷重移動量は▲25kg。
フロントタイヤに伝わる荷重移動量は▲75kgです。
つまり、前後ホイールレート2kg/mmのスプリングを装着したサスペンションのフロント側スタビライザ
ーだけを強化して横ロール量を半減すると、前輪の荷重移動量は100kgから150kgに増え、後輪の荷
重移動量は100kgから50kgに減るのです。
普通のタイヤ・・・すなわち、荷重と摩擦力が正比例しないタイヤに於いては、左右方向への荷重移
動量が増えると左右輪の合計摩擦力が小さくなりますので、そういったタイヤを使用する車両に於い
て フロントのスタビライザーだけを強化した場合、アンダーステア傾向に拍車が掛かるようになります。
なお、このようにフロントのロール剛性をリアよりも著しく高めた場合、効きの強い機械式LSDを装着
したFF車において、強い横Gの掛かる旋回中にオーバーステアの挙動を示すことがあります。
その理屈を「【荷重移動】荷重移動についてもう少しだけ詳しい話 006 「リアだけが異常に柔らかい
セッティングに生じる現象」へ記載しております。
よろしければご参照下さいませ。
※ 注記:ただ、この効果もあくまで紙の上の計算結果であって、実車、とりわけスポーツモデルではない普通のクルマにおい
ては、フロントサスペンションに比べてリアサスペンションを柔らかくしても、ここまで大きく前後で荷重移動量が変わることはあ
りません。
その理由は単純で、実際の車両(ボディ)は撓るからです。片側のジャッキアップポイントへ1Gの高さでウマを咬ませて、もう
片側のジャッキアップポイントを1箇所だけ持ち上げた場合、持ち上げた側の前後フェンダーと車輪の隙間は、違う速さで広が
って行きます(チュウイ:ウマを咬まさずタダ単に1箇所のジャッキアップポイントを持ち上げると、対角に在るサスペンションが縮
んで力が逃げます。 そのために、余程無茶に揚程を多くしないと片側の前後両輪を同時に持ち上げることは困難になりま
す)。
そして、十分に持ち上がった車両のドアを開けようとしても、動きが渋く、スムーズに開閉できません(チュウイ:ウマを咬まさ
ずタダ単に1ヶ所のジャッキアップポイントを持ち上げると、対角に在るサスペンションが縮んで応力が逃げます。 そのため、
意外にドアの開閉はスムーズです)。
そして勿論、上述の重心高さの変化も絡みますが、あまり剛性の高くない市販状態の車両では、ボディの撓りが影響するた
め、たとえば上例のようにリアサスペンションのホイールレートをフロントの3分の1にしても、「フロントの荷重移動量がリアの3
倍!」までは至らず、もう少し小さい数字になります。
|
|
|

|