|

更新の際に構造を変える事があります。 構造を変えるとアドレスが一から再配分されますので
ブックマーク等でお気に入りのページに飛んだ際に、目的と違うページが表示されることがあります。
その場合は画面一番下の [ TOP ] からトップページへ移動して、トップページから
目的のページへ移動してください。 お手数ですがよろしくお願いいたします。
実践ドライヴィング・テクニック
|
|
【問】昔のドラテク本を読むと必ずと言って良い程「立ち上がり重視のライン取り」という言葉が出てきま
す。 しかし、軌跡が最短に成るラインが一番速いのではないでしょうか?
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
【答】コーナーリングのライン取りは大雑把に言って3種類あります。
一つは、クリッピングポイントをコーナー出口側に近づけて加速区間を長く取る「立ち上がり重視のライ
ン」。
一つは、クリッピングポイントをコーナー入り口と出口の中間に取り、かつ鋭角的に曲がることによって
旋回区間を短く、減速・加速区間を長く取る「軌跡が最短になるライン」。
最後の一つは、、クリッピングポイントをコーナー入り口と出口の中間に取り、かつ旋回半径を可能な限
り大きく取る「旋回速度重視のライン」。
この3つです。
いずれを採るのが最速になるか――あるいは、どれとどれの中庸を採れば最速になるのか――は、そ
のコーナーのレイアウトやクルマの性能によって異なります。
ただ、昔のクルマの様にタイヤの性能が低く、[ 加速G ] < [ 減速G ] の差が大きいクルマは立ち上が
り重視のラインの方が速い傾向があります。
簡単に説明しておきましょう。
下図の縦軸が速度,横軸が時間です。
左端がコーナーAからの脱出地点,右端がコーナーBへの進入地点です。
青色の破線が「コーナーの軌跡が最短となるライン」を通った場合の速度変化だとします。
そうすると、進入速度を犠牲にして脱出速度を上げる「立ち上がり重視のライン」を通った場合の速度
変化が緑色の実線になります。

さて、コーナーAとコーナーBの距離は、下図における五角形ABCDEの面積に相当します(速度×時
間)。
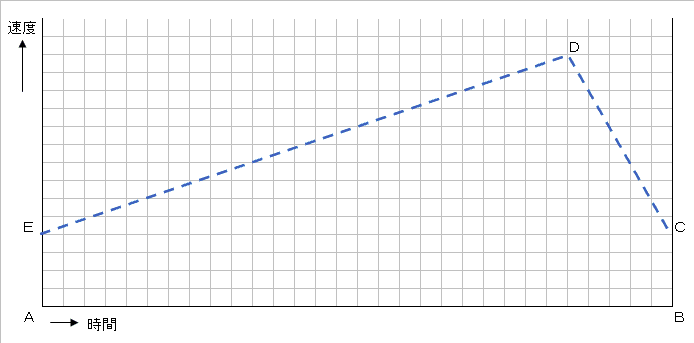
同じ面積を緑色の実線で囲んだ場合、下図の五角形AB’C’D’E’になります。
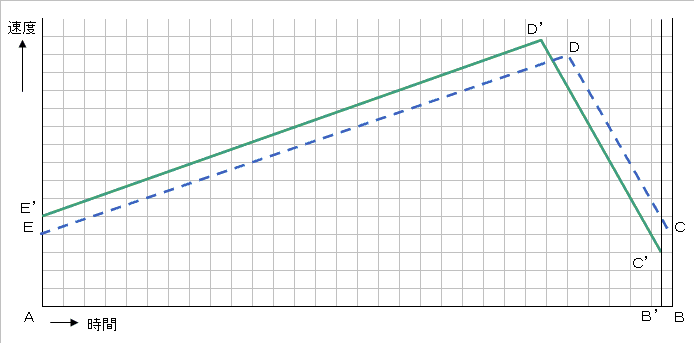
つまり、[ 加速G ] < [ 減速G ] の差が大きいクルマは進入速度を犠牲にしても、立ち上がり速度を稼
げば B-B'分だけ区間タイムを短縮できるのです。
しかし現在はタイヤやサスペンションの性能が上がり、旋回速度は元より、旋回制動性能も旋回加速性
能も著しく向上しました。 それにより、旋回半径を小さくして、直線的な立ち上がり区間を確保するより
も、可能な限り旋回半径を大きくして旋回速度を上げる走り方が速く走れるようになりました。
そのため、「立ち上がり重視のライン」はほぼ死語となりつつあるようです。
|
|
|

|