|

更新の際に構造を変える事があります。 構造を変えるとアドレスが一から再配分されますので
ブックマーク等でお気に入りのページに飛んだ際に、目的と違うページが表示されることがあります。
その場合は画面一番下の [ TOP ] からトップページへ移動して、トップページから
目的のページへ移動してください。 お手数ですがよろしくお願いいたします。
サスペンション
【荷重移動】荷重移動についてもう少しだけ詳しい話 006
「リアだけが異常に柔らかいセッティングに生じる現象」
|
|
2006.09.08 かめ様より分かり難い旨の指摘を賜りましたので、解説を追加しました。
2006.09.17 ヘンテコなデチューンに伴う荷重移動の偏りに関する記述を追加。
2007.05.03 数式を簡素化。
2007.05.08 後半を図解。
ロワームの角度によってロールやピッチ運動が抑制されたり、助長されたりするという理屈は御理解
頂けたことと存じます。
さて、ここで思い出して(あるいは参照して)欲しい記述があります。
それは、【スタビライザーの強化】です。
その重量配分に応じて適切に設定されたスタビライザーが前後に装着されていた場合、そのスタビラ
イザーは単純にロールを抑制します。
したがって、それ自体は荷重移動量に影響しません。
永くウォッチングして頂いている貴兄以外は御存知無いと思いますが、今年(平成18年)の3月に関東
地方某市にあるジムカーナ系チューニングショップの店長を名乗る者から、彼自身の輝かしい履歴を
添えた挑発的なメールを頂戴した際に、火病ってしまうという醜態を晒してしまいました。
この時の彼の思い込みが「固いスプリング・強化スタビライザにすると荷重移動量が増える」というもの
でした。
確かに前後どちらか一方のスタビライザーを重量配分比に不相応なまで強化、もしくは取り外してしま
うようなデチューンを施した場合、荷重はスタビライザーの拘束力の強い方へ偏ります(理屈は後述)。
しかし、前後に(前後のレート比が重量配分比やレバー比に対して適切な)スタビライザーを装着する
のであれば、前後に太いスタビライザーを装着しても、前後に細いスタビライザーを装着しても荷重移
動量は変化しません。
これは、『[ 001 ] 箪笥を押す時の荷重移動』で説明した通りです。
ところが、彼は、その延長に「荷重移動が増えるとトータルグリップ力が上がる」というオリジナリティ溢
れる理論が披露して下さいました。
既に実証済みの物理を根本から覆すオリジナル理論をぶち上げてまで何を理論付けたいのかという
と、「フロントサスペンションのバネレートをターマック仕様の硬いモノにし、リアを極端に柔らかくした場
合に、競技中の車両がオーバーステア傾向を示す」という実体験が既知の理論と噛み合わないからだ
そうです。
たしかに既知のセオリーとして、サスペンションスプリングを硬くすると両輪のトータルグリップ力は小さ
くなり、逆に柔らかくするとトータルグリップ力が大きくなります。 これは勿論、硬いサスペンションス
プリングの路面追従性が柔らかいサスペンションスプリングよりも劣るからに他なりません。
また、あまり一般的なセッティングではありませんが、前後どちらか片方だけサスペンションスプリング
を硬く(あるいは柔らかく)した場合、相対的に硬い側の荷重移動量が多くなって、硬い側の両輪のトー
タルグリップ力が小さくなります。
そして、その理屈はスタビライザーを前後どちらか片方だけ太く(あるいは細く)した場合にも当て嵌ま
ります。
この理屈について、簡単に説明しておきましょう。
とりあえず、前後どちらか片方だけサスペンションスプリングを硬く(あるいは柔らかく)した場合につい
て説明します。
話を簡単にするため、ロワアームジオメトリのロール抑制効果やブッシュ&スタビの介在などは全て無
視します。
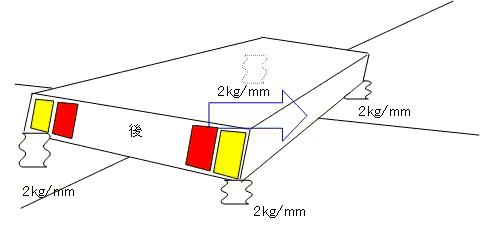
余り上手な図にならなくてゴメンナサイ(というか、メッチャ面倒臭いんですYO)。
コレ↑でもクルマのモデル図のつもりです。
(もちろん、表記のバネレートはホイールレートです)
青色の矢印が遠心力で、遠心力を受けて右側のスプリングが縮んでいます。
この時のクルマ全体の荷重移動量は、
重心高:50cm(0.5M)、
トレッド幅(タイヤ接地面両端部幅):1.5M
のクルマがG:0.5で旋回するとき、
[ 遠心力 ] = 1200(kg) × 0.5(G) = 600(kg)
[ 荷重移動量 ] = 600(kg) × 0.5(M) ÷ 1.5(M) = 200(kg)
平衡状態で左右輪の荷重はそれぞれ 1200kgの半分で600kg。
これに200kgの荷重移動が発生するのですから、片側の荷重が100kg増えて、もう片側の荷重が
100kg減ります。
つまり、外側前後2輪の合計荷重が600kgから700kgに増え、同時に内側前後2輪の合計荷重が
600kgから500kgに減るのです。 繰り返し述べてきた通り、バネの伸縮に伴って重心が移動する点を
無視すれば、バネレートは荷重移動量に影響しません。
重心位置が俯瞰してセンターに在るなら、前輪が負担する荷重の移動量は後輪が負担する荷重の
移動量と同じで、それぞれ 100÷2=50(kg) です。
ちなみに、この時のロール量は右側前後のバネが荷重移動100kgを受けて縮み、左側前後のバネ
が荷重移動▲100kgを受けて伸びます。
車両片側のバネレートは 2(kg/mm:前) + 2(kg/mm:後) = 4(kg/mm) ですから、
右側が 100(kg) ÷ 4(kg/mm) = 25(mm) 縮んで、
左側が 100(kg) ÷ 4(kg/mm) = 25(mm) 伸びます。
さて、では前後で異なるバネレートにしたらどうなるでしょうか?
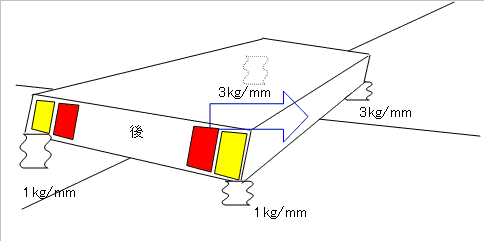
クルマ全体の荷重移動量は変わりません。 この場合も、
重心高:50cm(0.5M)、
トレッド幅(タイヤ接地面両端部幅):1.5M
のクルマがG:0.5で旋回するとき、
[ 遠心力 ] = 1200(kg) × 0.5(G) = 600(kg)
[ 荷重移動量 ] = 600(kg) × 0.5(M) ÷ 1.5(M) = 200(kg)
です。
そして、ロール量も変わりません(※ 厳密に言うと実車に於いては「違う」。 それについては後で注記)。
ロール量が変わらない理由は、片側前輪と片側後輪を合わせたレートが
3(kg/mm:前) + 1(kg/mm:後) = 4(kg/mm)
で、前後とも2kg/mmの時と同じだからです。
したがってロール量も
右側が 100(kg) ÷ 4(kg/mm) = 25(mm) 縮んで、
左側が 100(kg) ÷ 4(kg/mm) = 25(mm) 伸びます。
ですが、[ 前輪が負担する荷重の移動量 ] と [ 後輪が負担する荷重の移動量 ]は同じではありませ
ん。
それはこーゆー↓理屈です。
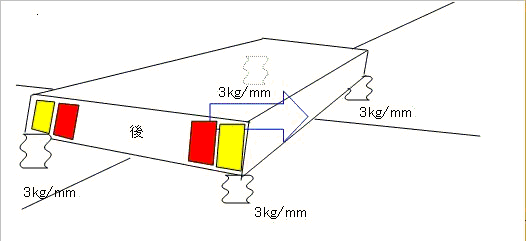
もし、すべてのサスペンションのスプリングが硬かったとしたら、↑このようにロール量が少なくなるハ
ズです。
逆に、すべてのサスペンションのスプリングが柔らかかったとしたら、↓このようにロール量が多くなる
ハズです。
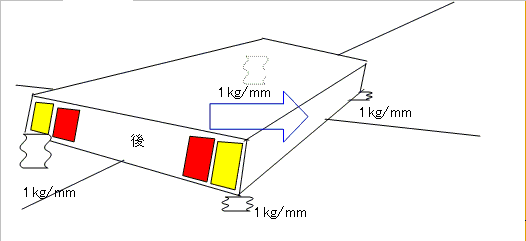
・・・ということは、前輪のスプリングが硬く、後輪のスプリングが柔らかい時は、「前輪のスプリングが
支えることに因って(全部のスプリングが柔らかい時に比べて)ロールが抑制されている」と見ることが
出来ます。
さて、理解して頂くために少しだけ違う話をします。
たとえば、バネ秤に100gの物を載せて、皿の高さが5cm沈んだとします。
突っかえ棒か何かを当てて皿の降下量を半分に抑えたら、秤の針が示す数字は、50gです。
もうだいたいオチが読めてしまったと思いますが、一応未だネタバレしていないという前提でハナシを
進めます(笑)。
すべてのサスペンションスプリングがホイールレートで1kg/mmの時、車両片側のレートは 1(kg/mm:
前) + 1(kg/mm:後) = 2(kg/mm) ですから、
右側が 100(kg) ÷ 2(kg/mm) = 50(mm) 縮んで、
左側が 100(kg) ÷ 2(kg/mm) = 50(mm) 伸びます。
つまり、100kg/mmを受けて本来なら50mm伸び縮みしているハズのホイールレート1kg/mmのバネ
が、ホイールレート3kg/mmのバネに邪魔されて25mmしか伸び縮みしないワケです。
先ほどのバネ秤の例は、荷重を受けて縮む量が減らされたために、秤のメカへ伝わるべき荷重が
減 らされてしまい、結果として秤の針が指す数字が小さくなっていました。
それはクルマのサスペンションでも同じです。
荷重を受けて縮む量が外部(この場合は前輪のバネ)の影響を受けて減らされると、タイヤに伝わる
荷重が減るのです。
もちろん、この物理は伸び側にも作用しますので、荷重を受けて伸びる量が外部(この場合は前輪の
バネ)の影響を受けて減らされると、タイヤに伝わる荷重が増えます。
計算上は、本来なら50mm縮んでいるハズのホイールレート1kg/mmのバネが、ホイールレート3kg/
mmのバネに邪魔されて25mmしか縮まないのですから、リアタイヤに伝わる荷重移動量は50kgではな
く25kg。
片側前後輪で100kgも荷重移動しているのに、後輪が25kgしか荷重移動をタイヤに伝えていないので
すから、前輪のタイヤに伝わる荷重移動は
100(kg) − 25(kg) = 75(kg)
です。
伸び側(イン側:上図では左側)でも計算式は同じで、リアタイヤに伝わる荷重移動量は▲25kg。
フロントタイヤに伝わる荷重移動量は▲75kgです。
つまり、前後ホイールレート3kg/mmのサスペンションスプリングをリアのみ変更してホイールレート
1kg/mmにすると、前輪の荷重移動量は50kgから75kgに増え、後輪の荷重移動量は50kgから25kgに
減るのです。
普通のタイヤ・・・すなわち、荷重と摩擦力が正比例しないタイヤに於いては、左右方向への荷重移
動量が増えると左右輪の合計摩擦力が小さくなりますので、そういったタイヤを使用する車両に於いて
リアのスプリングだけを柔らかくすると(前述の重心高さ変化の影響よりも左右方向への荷重移動の影響の方が強い
ので)アンダーステア傾向に拍車が掛かるようになります。
※ 注記:ただ、この効果もあくまで紙の上の計算結果であって、実車、とりわけスポーツモデルではない普通のクルマにおい
ては、フロントサスペンションに比べてリアサスペンションを柔らかくしても、ここまで大きく前後で荷重移動量が変わることはあ
りません。
その理由は単純で、実際の車両(ボディ)は撓るからです。片側のジャッキアップポイントへ1Gの高さでウマを咬ませて、もう
片側のジャッキアップポイントを1箇所だけ持ち上げた場合、持ち上げた側の前後フェンダーと車輪の隙間は、違う速さで広が
って行きます(チュウイ:ウマを咬まさずタダ単に1箇所のジャッキアップポイントを持ち上げると、対角に在るサスペンションが縮
んで力が逃げます。 そのために、余程無茶に揚程を多くしないと片側の前後両輪を同時に持ち上げることは困難になりま
す)。
そして、十分に持ち上がった車両のドアを開けようとしても、動きが渋く、スムーズに開閉できません(チュウイ:ウマを咬まさ
ずタダ単に1ヶ所のジャッキアップポイントを持ち上げると、対角に在るサスペンションが縮んで応力が逃げます。 そのため、
意外にドアの開閉はスムーズです)。
そして勿論、上述の重心高さの変化も絡みますが、あまり剛性の高くない市販状態の車両では、ボディの撓りが影響するた
め、たとえば上例のようにリアサスペンションのホイールレートをフロントの3分の1にしても、「フロントの荷重移動量がリアの3
倍!」までは至らず、もう少し小さい数字になります。
以上の点、つまり、前後どちらか一方のサスペンションスプリングを(もちろんホイールレートで)硬く(あるい
は 柔らかく)すると荷重移動が硬い側に偏るという点だけに着眼しましょう。
そうすると、某ジムカーナショップの「リアサスペンションだけをメチャに柔らかくする」というセッティン
グ を行えば、アンダーステア傾向が強くなるハズです( この理屈はスタビライザーの場合にも成立します。 たと
えば、リア側のスタビライザーを敢えて細くしたとします。 そうすると、前輪の太いスタビライザーの制約を受けて、本来なら
もっと多く伸び縮みしているハズのリアサスペンションが伸び縮みしなくなってしまうのですから、荷重が前輪側へ偏ります)。
少なくとも、そのセッティングの車両に普通のタイヤ・・・すなわち、荷重と摩擦力が正比例しないタイ
ヤを履かせば、アンダーステア傾向に拍車が掛かるようになります。
でも、フルスリックタイヤやSタイヤは、『ガチガチの功罪』でも触れた通り、ロードインディクスの限界
に達するまで、荷重と摩擦力がほぼ正比例するという特性を持ちます。 そのため、前後でバネレー
トを変えて荷重移動量がバネの硬い側へ偏っても左右合計摩擦力は、前輪も後輪も大して変化しない
のですね、実は。
左右の合計摩擦力が変わらないということは、ヨー角加速力が変わらないということですから、重心
高さの変化を考慮しない限り、スリックタイヤやSタイヤでの前後のバネレート差に因るステア特性への
影 響は余り大きくないと言えます。
というワケで、スリックタイヤやSタイヤの場合、前後でバネレートを変えたりスタビライザーの太さを
変えたりしてもステア特性はあまり変わらないようです。
でも、それでは、「フロントサスペンションのバネレートをターマック仕様の硬いモノにし、リアを極端に
柔らかくした場合に、競技中の車両がオーバーステア傾向を示す」という実体験を説明することが出来
ません。
いったい、「フロントサスペンションのバネレートをターマック仕様の硬いモノにし、リアを極端に柔らか
くした車両」の運動に何が起こっているのでしょうか?
実は、「フロントサスペンションのバネレートを硬く、リアサスペンションのバネレートを柔らかくした場
合」に起こっている【荷重移動の偏り】が、Sタイヤ&機械式LSDを装着したジムカーナ仕様車にちょっ
としたイタズラをしてしまうのです。
これ以降の詳しい解説を御覧頂く前に、別ページの拙稿【Sタイヤは、左右輪間で荷重移動しても左
右輪の合計グリップ力の低下が少ないのは何故】を読んでください。
あそこに書いた内容から必要事項を抜粋すれば以下の通り。
Sタイヤなどのケース剛性が高いタイヤは、強い旋回Gを受けても、
[ 前輪の左右間荷重移動量 ] > [ 後輪の左右間荷重移動量 ]
とはなるものの、タイヤの接地面の面圧が均一であるが故に
[ 前輪の摩擦力変化(低下) ] と [ 後輪の摩擦力変化(低下) ]
の差が少なく、ステア傾向の変化は僅かしか起こりません。
そして、Sタイヤなどサイドウォールの剛性を上げてあるタイヤは、大きな荷重を受けながら横力を発
揮しても歪まないので、大きい摩擦力を失いません。
では、以上を踏まえた上で、本論に進みましょう。
まずは、旋回に伴う荷重移動を図示してみます。
ノーマルサスペンションもしくは前後を均等に強化したサスペンションの場合
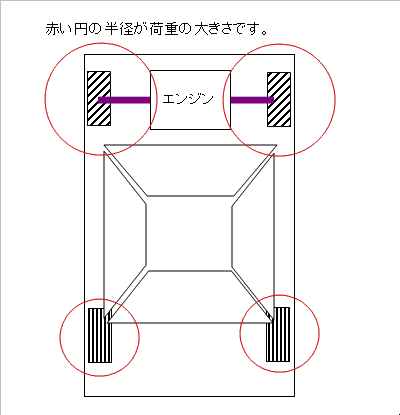
旋回中はアウト側へ荷重移動する為に、赤い円の大きさが変化します。
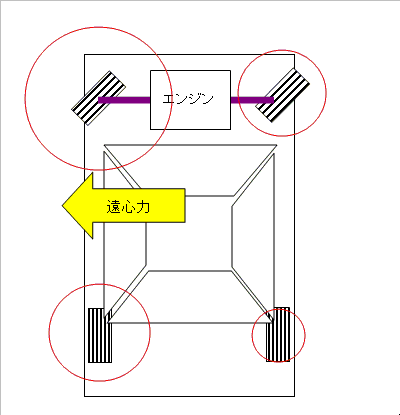
ここで前後輪でロール剛性に差をつけると
ロール剛性の高い側に荷重移動量が偏ります。
フロントサスペンションのスプリングをガチガチに、リアサスペンションのスプリングをフニャフニャにす
るなどして、前後輪のロール剛性比を大きくすれば、それがそのまま荷重移動の偏りになります。
たとえば、車両重量1000kg,重心高さ50cm,トレッド幅1500mmのクルマが0.8Gで旋回すると
車輌に生じる荷重移動量は
[ 遠心力 ] =1000kg×0.8G=800kg
[ 荷重移動量 ] =800kg×0.5M÷1.5M=600kg
となります。
このクルマの前後輪のロール剛性比が5:1だったとしたら、
車輌全体で600kgの左右間荷重移動量の内、500kgが前輪の左右間荷重移動量,100kgが後輪の左
右間荷重移動量になります。
車両重量の前後軸重配分が7:3だったとしたら、
水平方向のGが無く、ローリングもピッチンングもしていない時の前軸重量700kg
→ 前輪左右タイヤ荷重は700kg÷2=350kgずつ
それが上図のように右旋回して500kg荷重移動すれば、
前輪アウト側=350kg+(500kg÷2)=600kg
前輪イン側=350kg−(500kg÷2)=100kg
です。
同様に、水平方向のGが無く、ローリングもピッチンングもしていない時の後軸重量300kg
→ 後輪左右タイヤ荷重は300kg÷2=150kgずつ
それが上図のように右旋回して100kg荷重移動すれば、
前輪アウト側=150kg+(100kg÷2)=200kg
前輪イン側=150kg−(100kg÷2)=100kg
図示すれば、旋回中の荷重配分が↓こんなに凄いことに!
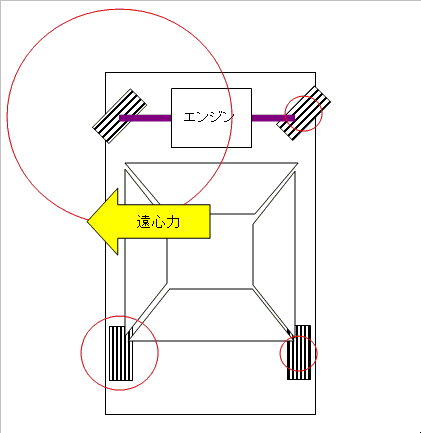
さて、この荷重変化に対して摩擦円の大きさは
どう変化するでしょう
青い円の半径が摩擦力である
分かり易くするため、荷重移動のない前2輪荷重の大きさ(半径)と
その時の摩擦力の大きさ(半径)を同じに図示します。
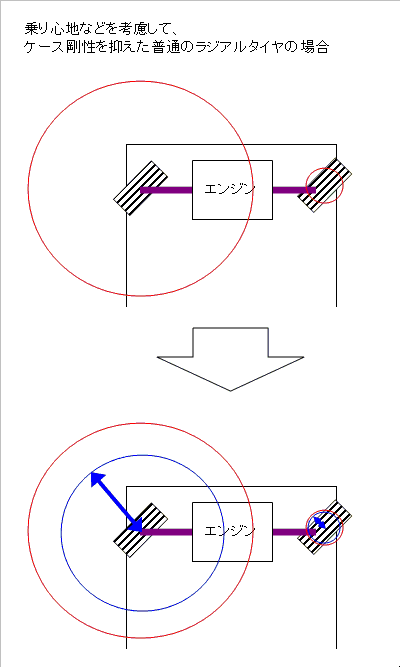
荷重が減る分には、
荷重の大きさにほぼ比例して摩擦力が小さくなりますが
荷重が増えて発生する横力が増えると
スチールベルトが歪んで接地面圧が減るので
摩擦円の大きさが荷重の大きさよりも小さくなります(上図のように)
駆動輪による加減速がない場合に
左右輪の摩擦円半径の合計(※)が最大旋回速度を決めます。
※ 二つの青い矢印の大きさの和
当然のことながら、左右輪間の荷重移動量が少なければ、
荷重の大きさと摩擦力の大きさの差が小さくなる(摩擦力の飽和から遠ざかる)ので
左右輪の合計摩擦力(二つの青い矢印の合計長さ)は、大きくなります。
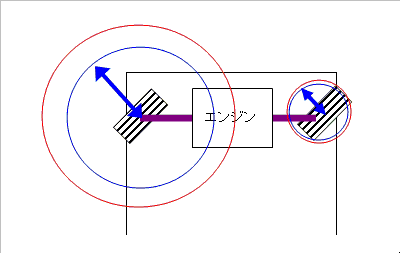
つまり、ケース剛性のあまり高くない普通のタイヤで、前が強いロール剛性比にした場合、
アンダーステア傾向が強まるワケです。
さて、このクルマが旋回加速したらどうなるでしょうか?
旋回加速をする場合は、タイヤの摩擦力が駆動力に割り引かれるため、
(ベクトルの引き算で)[ 摩擦円半径 ] − [ 駆動力 ]
が求心力を生む余力となります。
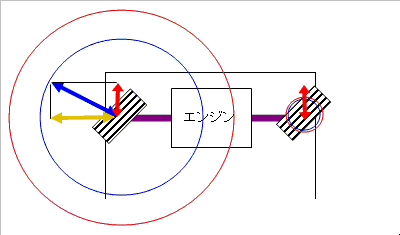
御覧の通り、強く加速するとイン側は駆動力(赤い矢印)だけを支えることすら出来ません(LSDが無
ければ空転)。
しかし、強いLSDで差動が制限されていれば、少なくとも摩擦円の大きさ分だけはイン側タイヤが駆
動します。
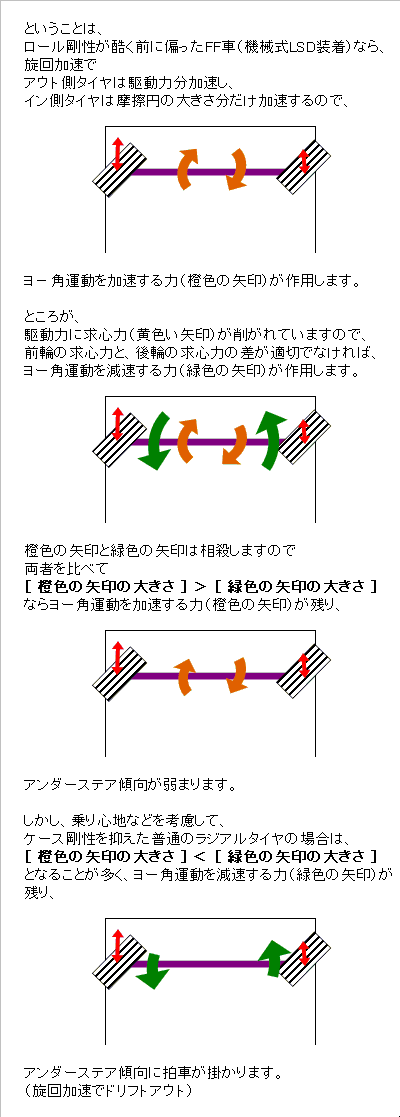
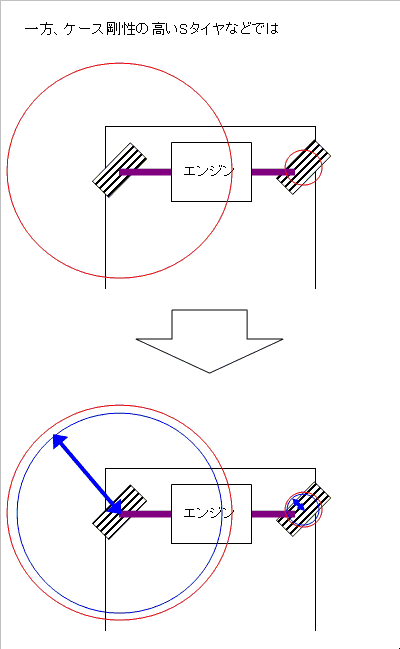
荷重が小さくなれば同程度摩擦力が小さくなるのは同じですが、荷重が増えて発生する横力が増え
てもスチールベルトが余り歪まず、接地面圧が均等に近いので、荷重が大きくなれば摩擦力も同程度
大きくなります。
つまり、荷重の変化と摩擦力の変化が正比例に近いため、大きな荷重の掛かっているタイヤの摩擦
円が大きいのです。
当然のことながら、強い駆動力を与えて求心力が大きく削がれても、余裕綽々です。
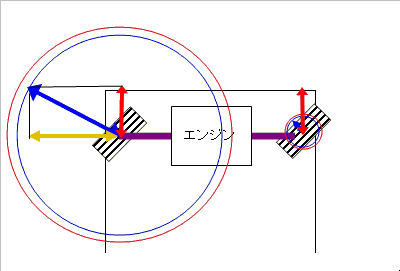
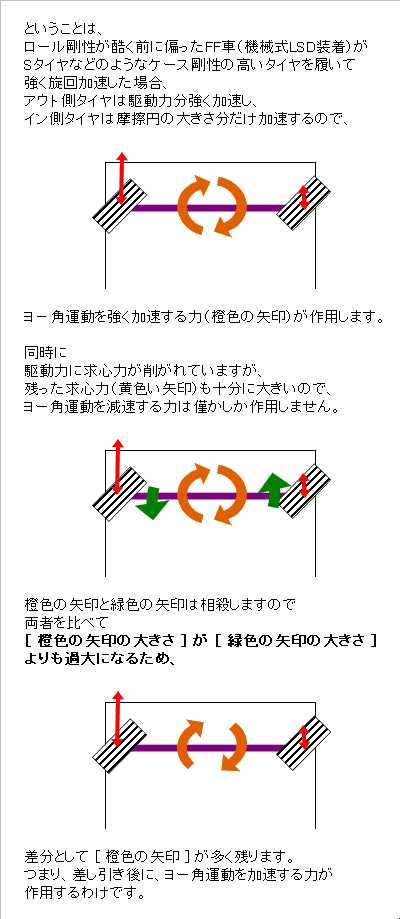
ロール剛性が酷く前に偏ったFF車(機械式LSD装着)が、Sタイヤなどのようなケース剛性の高いタイ
ヤを履いて強く旋回加速した場合に、アンダーステア傾向の著しい弱化(≒オーバーステア=スピンモ
ードへ移行する挙動)を示すことがあるのは、以上の理由に拠ります。
摩擦円よりも強く駆動することは出来ませんから、荷重が大幅に軽くなって接地圧が下がると駆動力
が地面に伝達する効率が落ち、荷重の大きいタイヤの駆動との差でヨー角運動が加速されるワケで
す。
・
・
・
延々実に6ページ。 長々と綴って来ましたが如何でしたでしょうか。
安易に語られがちな用語【荷重移動】ですが、ホンの少し突っ込んで現象を捉えようとするだけでこん
なにも奥が深いのです。
もちろんこれだけが全てではありません。
解説の楽なストラットサスペンションに限って説明しましたが、他の構造のサスペンションではロール
抑制やダイブ・スカット抑制の作用原理が違ってきますし、ジャッキアップ/ダウン現象もサスペンション
の構造で随分違います。
ただ、我々はタダのクルマヲタクでしかなく、自動車工学の知識を極めたからといって自動車メーカー
でサスペンション設計に関われるワケではありません。
自分や友人が使うクルマのサスペンションやエンジンにおいて間違ったチューニングをしないようにす
るのが関の山です。
その程度にしか役立たなくても、「知っている」と「知らない」の間には大きな隔たりがあります。
もし私のホームページを読んで自動車工学に興味を持って頂けたなら、図書館で借りるので結構で
すから、是非一度モノホンの自動車工学書に目を通してみて下さい。 あくまでノーマルエンジン/ノー
マルサスペンションに関する記述しか載っていませんが、クルマに働く物理にノーマルもチューンドも関
係ありません。
ノーマルの理屈を知ればチューンドの理屈が見えてきます。
本拙稿がその一助になれば何よりの悦びです。
ではでは。
|
|
|

|